〝珍字〟を通して漢字世界の奥深さを知る:「『漢和辞典』に載っているヘンな漢字」
2014年4月2日
2008年発行。進藤英幸監修、高井ジロル著。二見書房。
漢字ほどなじみある文字はないのだが、Wikipediaによるとなんでも10万文字を超えているとか。この数字を見ると、みんなが自由自在に使っていると思われる漢字も全体のほんの一部でしかないことがわかる。また、漢字を使う言語はアルファベットだけで表現する英語などとは異質なのも実感する。
この本は、ぼくらとはまず縁がないようなマイナーな漢字を「ビジュアル的に面白い」という切り口で選び出して紹介する。とはいえ、難しい内容でなく、確かに「なんだこれw」と笑ってしまうような不思議な漢字が並ぶ。そして、専門家である進藤氏が解説をしながら、それにライターの高井氏がツッコミをいれたりボケをいれたりと、面白く読める構成になっている。
紹介されている漢字もさまざま。
「馬」に「鹿」で「馬鹿」と思いきや、体の小さい馬を表す「![]() 」。
」。
「諸橋大漢和」の別名がある大修館書店の「大漢和辞典」で最も画数が多い「![]() 」を知っている人は少なくないと思う。「林」が4つ合体した「
」を知っている人は少なくないと思う。「林」が4つ合体した「![]() 」というくどい字もある。ちなみに意味は未詳らしい。シンプルな例では「
」というくどい字もある。ちなみに意味は未詳らしい。シンプルな例では「![]() 」。カタカナの「ナ」と思いきやれっきとした漢字で「左」の本字だという。
」。カタカナの「ナ」と思いきやれっきとした漢字で「左」の本字だという。
「![]() 」はもちろん「猪木」ではなく「姓名や物事を記入して立てる木の札」。「
」はもちろん「猪木」ではなく「姓名や物事を記入して立てる木の札」。「![]() 」もやっぱり「山田」ではなく「邦」の古字。全国の山田さんは話のタネにもってこいといったところ。
」もやっぱり「山田」ではなく「邦」の古字。全国の山田さんは話のタネにもってこいといったところ。
「家」にしては何か足りない「![]() 」は「家の中で静かにひっそり」の意味。逆に「馬」にしては棒が1本多い「
」は「家の中で静かにひっそり」の意味。逆に「馬」にしては棒が1本多い「![]() 」は「1歳の馬」を指す。「
」は「1歳の馬」を指す。「![]() 」は「予」の写植ミスかと思いきや「幻」の本字でれっきとした漢字。漢字にしては曲線美がある「
」は「予」の写植ミスかと思いきや「幻」の本字でれっきとした漢字。漢字にしては曲線美がある「![]() 」や、どこかの中小企業のマークみたいな「
」や、どこかの中小企業のマークみたいな「![]() 」だって立派な漢字。
」だって立派な漢字。
こんな変わった感じがずらずらと紹介されているのだが、先ほども書いたように進藤氏と高井氏の軽妙なやりとりで字義やなりたちなどを学ぶことができる。何より気楽に読めるのがいい。大人が読むのも面白いし、子どもにも読ませたい本だと思う。
面白いもので、こういう「面白い」視点から入るとちょっと難しそうな分野である漢字の歴史やその深い世界に興味を強く抱いてしまう。またぼくらが何となく使っている常用漢字ですら、そのバックグラウンドにはいろいろな経緯があることを推測できる。何となく使っている漢字だが、そこには先人のいろいろな知恵が込められているのだなあと実感してしまう。
思えばたまに調べ物で漢和辞典を繰ると、今まで知っていたのとは違う字の意味を発見することもあり、自分の無学と漢字の奥深さに気付くことがある。いつも使っている漢字もほんの少しの側面でしかない。恐ろしいほど長い年月をかけて積み上げられてきた漢字という文化のほんのはじっこしか使っていないことが分かる。もちろんそれで用が足りているのでいいのだが、せっかく漢字文化圏に住んでいるのだからもっといろいろと知りたくなる。そんな知的好奇心をくすぐる本だった。
なお、このエントリで使っている漢字のgifデータは、この本でも紹介されている島根県立大学e漢字フォント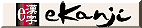 で公開しているデータを使わせていただいた。
で公開しているデータを使わせていただいた。
